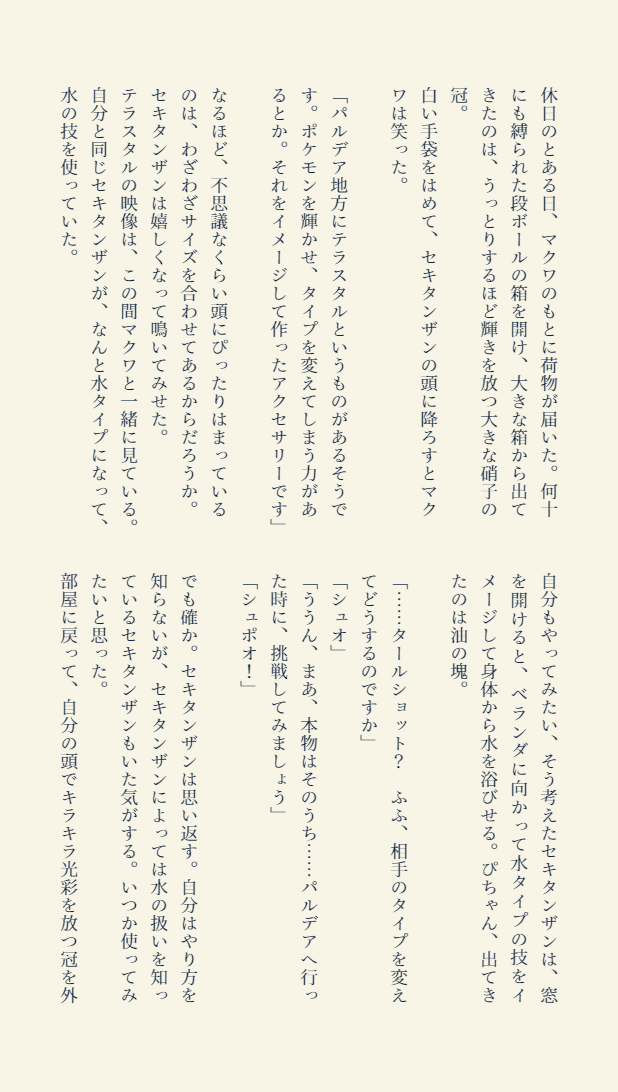大冒険はほんのミクロの中にあった。
たとえばオフの日。
相棒と一緒にいる最中でさえ、あっという間にマクワを異次元に連れて行ってくれた。
機材の準備は抜かりなし。大きな箱をがちゃりと開けば、階段状になった引き出したちが、整備士のを運ぶクレーンのように、ずらりと顔を並べだして、いつだってマクワはとてもいい気分になった。
彼らは優秀なオペレーターとして、マクワの手足そのものになって旅路を手伝ってくれるのだ。
気分も上がるので、これを買って良かったと心底思う。
もちろん中身だって負けていない。
いつだってピカピカに磨き上げられていて、旅立ちの準備はオールオーケー。
太さや大きさで揃えられた『先端』たちも、一つたりとも抜けはない。
わくわくした気持ちのまま、マクワは手前に伸びた引き出しから、鉄製の細い棒を一つ握りしめて、目の前に広がる深い闇の中にすっと先端を横にスライドさせた。
たったそれだけで、冒険は始まるのだ。天頂を穿つ白星が、光を受けて輝いた。
たっぷりの真っ暗闇を銀の尖星がしゅう、しゅっと流れていく。
凹凸の宇宙を駆け抜けて、うっすら黒を削り取り進んでいく白星。たったひとり、温かな闇の中を迷うことなく怜悧に駆け抜けていく。魔法の輪郭線を描いていく。
黒い粉をぱっぱと躍らせながら、戻っては大きく進む、戻っては大きく進む。
航路は必然。「暗闇」のある場所、ただそれだけだ。
分厚く立ちはだかる黒を、塵芥よりもちいさく割って、彼の道が出来た。
ここは必要な隙間だ。スムーズに駆動するための溝。
基礎に近い場所。
その道筋を辿っていく度に、艶やかに磨かれた黒炭が青い光に触れて、悠然と瞬いていった。
見えないのに、何故か見える。石炭の陰、昏い場所。
だからこそ、もっともっと進んでいきたいと銀星は考える。
小さな星は、小さなまま随分と進んだ。十分すぎる程立派に、美しく出来た。
このままでも、きっと他の誰も十分だと言うだろう。
本人でさえ、いや、本人は一番どうでも良いと思っているに違いない。
だけど、今自分がきらきらと光っているのが分かる。せっかくだ、まだまだこの「旅路」を堪能していたい。
そう考えたマクワは、自分の形を――自分の使用する道具を替えることにした。
怜悧で細い器具を置き、次はざらついた細長い鑢を取り出して、再びセキタンザンの頭の下と睨めっこを始めた。昨日の試合でタールショットを使用し、零れた分が残って固まってしまったことはセキタンザンも自覚があった。
マクワも不足するよりは良い、試合後の手入はトレーナーの仕事の基本中の基本なのだから、常に余剰が出るようにと指示をしていた。
もちろんセキタンザンも試合で手加減するつもりはない。
その指示に従った。
そして今、その手入の最中なのだが。
なんだかいつも以上にマクワの気持ちが高まっているのか、それとも自分が乗り気でないだけなのか、セキタンザンにも判断はつかないが、とにかく退屈をし始めていた。
手入れしてもらうのは気持ちいい。
これもコミュニケーションの一つだ。
楽しいことに違いないはずなのだが、とにかくマクワを――気配をけしてしまうほど巧いのか何なのか、これもセキタンザンには判断がつかなかった――このちょうど視界からすっかり消えてしまう場所からでは、見つける事が出来なかったのだ。
マクワはずっと顎の下にいて、ずっと顎の下ばかりを集中的に手入していた。
しかも、あまり強い力ではなく、そっと、撫でるような力で研磨をしている。
セキタンザンはゆっくりと自分の身体を上に傾けて、マクワの作業から身体を遠ざけてみた。
マクワの手が届く範囲では、まだ何も言ってこない。もっと動かしたらどうなるだろう。
セキタンザンの好奇心が疼いた。
「セキタンザン! 動かないでください」
鋭く、しかし淡々とした声音が飛んで来た。しかしセキタンザンにとってはマクワの気を引く事が出来たことで、これはミッション成功の範囲だった。
では次に、マクワが作業しているまま一緒に運んでみたらどうなるだろうか。
セキタンザンは座り込んで自分の前に座るバディのお尻をゆっくりと持ち上げて、そのまま立ち上がった。邪魔はしていない。
「ちょっと……セキタンザン?」
「シュ ポォー」
「……動かないでと……。きみ、疲れましたね?」
溜息混じりでバディが見下ろしている。マクワの眼の色に少しばかり悪戯っぽい、勝ち誇ったような色が浮かんでいたのを読み取って、セキタンザンはあまり面白くなかったのだが、しかし今回ばかりはその通りなので小さく声を上げるだけに留まる。
「ボー」
「もう少しですから……忍耐の特訓です」
「シュォオ」
「うわ、ちょ、セキタンザンっ! ふふ、あはは!」
脇の下やお腹を擽る攻撃に出てみた。抱き止めた体勢のままだから、マクワは身動きをとる事が出来ない。逃げられない。
セキタンザンにとっては、もうとっくに忍耐の特訓だったのだ。そもそも手入はコミュニケーションのはずなのに、それを一方的に取り上げられている事自体、理不尽じゃないだろうか?
だからセキタンザンはコミュニケーションの時間を取り戻したい。そんな意思表示だ。
笑いすぎた丸い青い瞳からじわりと涙が滲んでいた。
「ストップ! わかりましたからっ! そうか。ぼくは勝手に良いことだとばかり思いこんでましたが……これはきみにとって何もわからないのですね?」
「シュポォ」
「それは残念ですね。ずっと仕上げをしていますし……やり方を考えるとしましょう。今から試しますので……きみが良いとおもったものを教えてください」
「シュ ポォー!」
大冒険はほんのミクロの中にある。しかしひとりきりでは到底難しい。
いつも自分の傍で煌々と聳え立ち、心躍る場所へと連れて行くのだ。