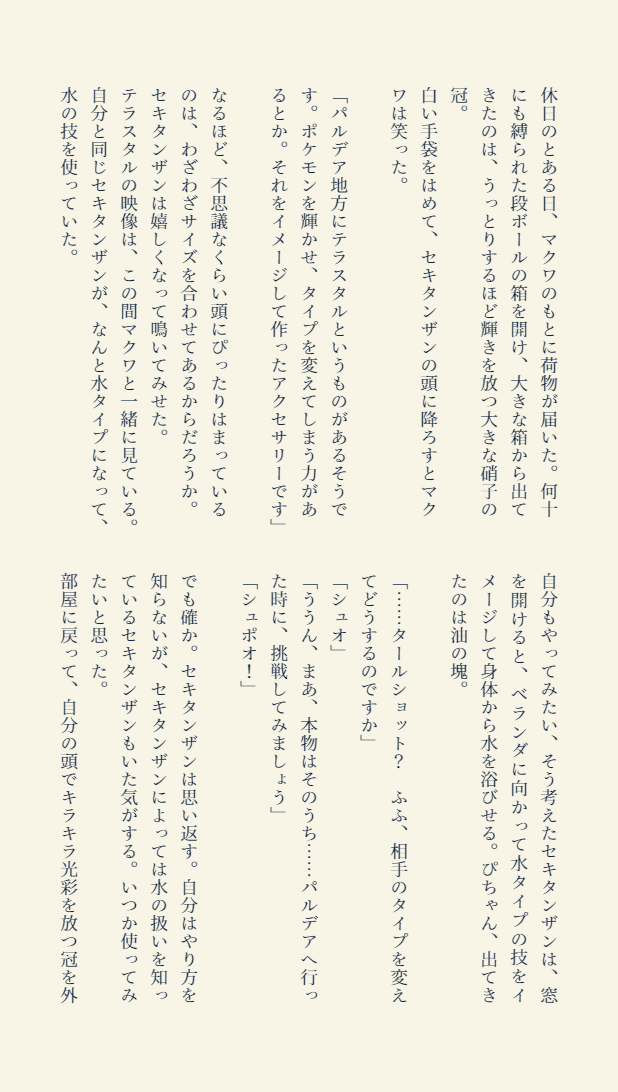凍えるような冷たさが、記憶の中で確かな重みを増して、頬を一つずつ刺してゆく。
既に日は沈み、夜空を彩るパシオの星空の下、マクワはざくざくと白雪を踏みしめながら、人工的に造られた氷のエリアを歩いていた。
この場所は、母メロンのお気に入りの訓練スポットだ。
確かに思い出の中のキルクスの雪山の雰囲気に近く、傾斜が多くてとても簡単に歩みを進める事は出来ず、氷雪は食料を奪い、体温を根こそぎ攫って行く。
この環境下であれば、ポケモンと共に峻厳な鍛錬が行えることは、マクワにも想像が出来る。
パシオという他地方に来たメロンは、早速この場所を見つけてひたすらトレーニングを行っているのだという。全く、母らしいと思う。
喧嘩をしている現在は、なるべく顔を合わせないようにしている身だ。
本来ならば放っておくものだが、ルリナが今日は帰りが遅いと心配をしているのを耳にしてしまった。
同地方の大切な同僚の為、一時休戦して、長く訓練を続ける母親の様子を伺い、迎えに行くことにした。
氷の輝く洞窟を潜り抜けて、雪積の斜面を登れば、見晴らしの良い高い丘の上に辿り着いた。
低木は皆雪をかぶって白く染まり、真っ白な雪の中で、真っ白な母親が雪の上に座り込んで、荒くなった息を整えている。
辺りにはポケモンは全く見当たらず、一人で筋トレでもしていたのだろうか。
一筋、冷たい風が首筋を通って吹き抜けて行く。
大丈夫だ。マクワは大きく一呼吸をついてから、バディの入るモンスターボールをそっと撫で、もう一歩足を進めた。霜雪はじゃり、と高らかに音を立て、マクワの来訪を彼女の耳に届かせた。
白雪の長い髪の間から、大きなアイスブルーを細めて、薄桃に色づいた唇でにっこりと笑う。マクワはサングラスを指で持ち上げた。
「あら、一緒にトレーニングする気になったのかい?」
「……違いますよ。もうこんな時間です、ルリナさんやポケモンセンターの方も心配をされていました」
「おや、本当だ。……まったく、もう少しくらい一日の時間ってのは、長くならないもんかね」
「なりませんよ。さあ、行きましょう」
「そこは”帰りましょう”じゃなくて?」
ゆっくりと立ち上がり、近づいたメロンの細長い白磁の指先が、マクワの柔い手首を掴んでいる。
振りほどこうとしたが、意外なほど力強いその手は離れていかない。
仕方なく、そのまま後ろを向き、マクワは先導して歩くことにした。
「……行きますよ」
「ここの夜も星がたくさんで綺麗だねぇ」
「そうですね。キルクスで見る星とは種類も大きさも、全く違って見えます。とても新鮮で、良い経験です」
「そうでもないよ。あたしには良く見える」
マクワは思わず瞬きをして、無数の星々輝く深い寒空を見上げた。
パシオはキルクスのあるガラルとはかなり距離があり、遠く隔たりのある場所だ。
見える星の種類は違っていて、当然だった。
「……え、本当ですか? 一体どれが……」
「あんたの所にねがい星が降って来た日の空の星たちがよく見えるよ」
「何言って……」
「なーんてね、それじゃあ行こうか」
あれほど強く握られていたはずの手が、するりと糸のように解けて消えていく。
立ちすくむマクワの前を、何も言わずメロンが雪を滑るようにして歩む。
「母さん……!」
マクワにはわからない。
母が自分に何を求めているのか。
ただ、ひとつだけ確実なことは、あの反旗を翻した時から母の時間は進んでおらず、原因である自分を取り込もうとする。
今のマクワはただ、無理矢理巻き戻された時間を何とか引きずり戻して、後を追うだけで精いっぱいだった。